こんにちは。知育玩具研究家のkurokoです。
今日はあの美しいネフスピールが一体どのように生まれたのか?
職人さんの試行錯誤や家族の協力のお話をお届けしたいと思います。
ネフスピールは、スイスで生まれた木製の知育玩具。
美しい曲線と職人の手仕事によって生まれたこの積み木は、子どもの創造力と集中力を育てる“遊びの芸術”として、世界中で愛されています。
この記事では、ネフスピールの誕生秘話を、温かなストーリー形式でご紹介します。
「長く使える積み木を探している」「感性や創造力を育てたい」そんな方にぜひ読んでいただきたい内容です。
*本記事は生成 AIを活用して作成しております。
第1章:木の香りと、ひとつの小さなひらめき
1957年、スイス・チューリッヒ近郊の町、シュタイナー。
丘に囲まれたこの小さな町は、春になると花畑に包まれ、冬は静かに雪が降る。石畳の道と古い木造の家々が並び、人々は名前で呼び合い、郵便屋は毎朝コーヒーを勧められるような場所だった。
そんな町のはずれに、木の香りが満ちる工房があった。
看板には「Naef」の四文字。目立たぬデザインだが、町の人々にとっては信頼の証だった。
クルト・ネフ、38歳。家具職人として20年以上のキャリアを持ち、頑丈で美しい木工製品を作ることで知られていた。
彼の手は大きくて節くれ立っていたが、木を撫でるときは信じられないほど繊細だった。硬い木も、彼の手にかかれば滑らかに、温もりをたたえた作品へと変わっていく。
この日も、工房ではオーク材のキャビネットの仕上げが進んでいた。ノミの音、鉋を引く音、木屑の舞う香り。クルトにとって、それは日常であり、静かな喜びだった。
工房の奥には、窓辺に花が飾られていた。
手入れをするのは、妻のアンナ。彼女はいつも淡い色のエプロンを着て、工房に小さな明るさを添えていた。
午前10時ごろ、アンナがカウンターから声をかけてきた。
「クルト、ちょっと来て。お客さんが面白いことを言ってるわ」
クルトは道具を置いて前に出た。そこにいたのは、近くの幼稚園で働く保育士、マルタ・シュトックリだった。明るい瞳と少し鼻にかかる声。町でも評判の“元気な先生”だ。
マルタは手に木製のスプーンを持っていた。以前、クルトが作ったサンプルのひとつだった。
「これね、子どもたちがすごく大事そうに扱うのよ。プラスチックのおもちゃじゃ見向きもしない子が、これには夢中になるの」
クルトは驚いたように眉を上げた。
「それは…意外ですね。ただのスプーンなのに?」
「“本物”だからよ。手に持ったときの重さ、木の匂い、手触り。子どもたちはちゃんと感じてるの」
そしてマルタは、ふとした一言を投げかけた。
「ねぇクルト。あなたの木工で、“子どものための本物”を作ってみない?」
その言葉が、工房の空気を少しだけ変えた。
「子どものために? 私の木工で…?」
クルトは一度笑いかけたが、途中で言葉を飲んだ。
彼の頭の中には、これまで作ってきたテーブル、椅子、棚が浮かんでいた。重厚で、使い込まれ、家族の記憶が刻まれるような家具たち。
だが、マルタの言葉は、まったく違う世界の扉を開こうとしていた。
「もしよければ、うちの園で試してみてもいいのよ。子どもたちは正直だから、すぐに反応するわ」
「……考えてみます」
クルトの返事は短かったが、その夜、工房の灯りはいつもより遅くまで消えなかった。
第2章:曲線のきらめき、はじまりのカタチ
クルトはその晩、布団に入っても眠れなかった。
寝室の天井を見つめながら、耳にはマルタの言葉が残っていた。
「子どものための、本物を」
なぜその言葉がこんなにも胸に残るのか。家具職人として長く生きてきた彼にとって、“本物”という言葉には誇りも、厳しさもあった。だが、それを“子どものために”と聞いたとき、なぜか心がざわついた。
「子どもが本物を必要とするなんて…」
その考えは、これまでの自分にはなかった視点だった。
翌朝、まだ陽も昇らぬうちにクルトは工房の明かりを灯した。
いつものように木材の前に立ったが、手は自然とスケッチブックを探していた。家具の設計では使い慣れていたが、今日描くのはまったく未知のものだ。
ページをめくり、鉛筆を走らせる。最初は四角い積み木、円筒形のブロック、簡単な動物の形など、既存の「おもちゃらしい形」が並んでいった。
(違う、何かが足りない…)
デザインは整っている。安全性も問題ない。しかし、心が動かない。
家具を作るときにはいつも感じる「これだ」という手応えが、まるで湧いてこなかった。
クルトは手を止め、窓の外を見た。
朝の光が差し込み始め、工房の隅に積まれた木の端材が淡く輝いている。その中に、一本の板が目に留まった。メープル材の切れ端。木目に沿って波のように滑らかなカーブを描いていた。
(これは…)
彼はその板を手に取り、そっと撫でた。
触れた瞬間、指先に伝わる滑らかさ。目で追うたびに形が変わるような不思議な感覚。それはまるで、一本のリボンのようだった。
「もし…これを積み木にしたら?」
その発想は、まるで電流のように全身を駆け抜けた。
家具と違って、積み木には機能がない。正確な角度や頑丈な構造も不要だ。必要なのは、可能性。それを遊ぶ子どもが、いかようにも想像していい「余白」だった。
直線でもなく、規則正しくもない曲線。
それを積み木にしたら、どうなるのか? どんな形が生まれるのか?
クルトは木材を机に固定し、細身のノコギリを取り出した。息を止め、慎重に曲線を描く。削り、削り、手の中で回転させ、磨く。ひとつのピースに20分以上かけた。
夕方までに、10個の“なにか”ができあがった。
曲線と曲線が重なり、ランダムに見えて絶妙な安定感がある。直線的な積み木では決して生まれない、動きと静けさの狭間。クルトはその美しさに、自分でも驚いた。
アンナが工房に顔を出したのは、夕食の準備の頃だった。
「クルト、もう日が暮れるわよ。…それ、何を作ってたの?」
クルトは笑みを浮かべて答えた。
「積み木…いや、もしかすると“新しい形の遊び”かもしれない」
アンナは興味深そうに手に取ったが、少し眉をひそめた。
「なんだか、難しそうね…。子どもが使いこなせるかしら?」
クルトの笑顔が少しだけ曇った。
そこに、見習いのフランツも工房に入ってきた。彼もピースを手に取り、軽く首をかしげた。
「クルトさん、芸術みたいだけど…これ、積めるんですか? むしろ飾ったほうがいいかも」
否定ではない。ただ、疑問。それでもクルトの心には、すでにひとつの確信があった。
「子どもに試してみればわかるさ」
彼はその夜、幼稚園に連絡を取った。マルタを通じて、子どもたちにこの積み木を遊んでもらえる機会を求めた。
園長のエミリー先生は快く承諾してくれ、次の週末、特別な“遊びの時間”が設けられることになった。
それが、ネフスピールの誕生を告げる最初の鐘の音だった。
第3章:はじめての“魔法”
週末の朝、シュタイナーの空は快晴だった。
冬の終わり、空気はまだひんやりしていたが、陽射しには春の兆しがあった。
クルトは、大きな木箱を抱えて幼稚園の門をくぐった。
中には、10個のメープル材のピース。滑らかに磨き上げられ、陽の光を受けるとほんのりと黄金色に光っていた。
園長のエミリー先生が迎えてくれた。
「ようこそクルトさん。子どもたち、朝から落ち着かないんです。『新しいおもちゃが来る』って、もう噂になってますから」
遊戯室に案内されると、カラフルな壁と小さなテーブルが並んでいた。
クルトはテーブルの中央に、ピースを一つずつ丁寧に並べた。
10個のピースはどれも違う形。くねるような曲線、波打つようなエッジ、そしてほんのわずかに傾いた重心。
整列させようとすれば、自然と少し揺れ動く。まるで、置かれるのを拒むように——けれど、そこに美しさがあった。
「さぁ、好きに遊んでみてね」
その言葉とともに、子どもたちがぞろぞろと入ってきた。
最初にピースを手に取ったのは、5歳のルーカス。小柄でやんちゃな男の子だ。
「なにこれー!へんなカタチ!」と笑いながら、両手にピースを持ってクルクル回し始めた。
次に近づいたのは、4歳のソフィー。おっとりとした女の子で、目を輝かせながらピースを撫でた。
「やわらかい木のにおい…リボンみたい」
だが、すぐに他のおもちゃに気を取られて離れてしまった。
クルトの心に、不安が忍び寄った。
(やっぱり、普通の積み木のほうが良かったのか…?)
しかし、次の瞬間——その流れは変わった。
6歳のハンスが、ゆっくりとピースをひとつ手に取り、じっと観察し始めた。
彼は無口な子で、いつもは一人遊びをしていることが多い。だが、その日、彼の目にはいつもと違う光が宿っていた。
慎重に、ピースを重ね始める。
バランスを取りながら、一つ、また一つ。ゆらりと揺れる塔が、3段、4段と伸びていった。
そして——5段目を乗せた瞬間、窓から差し込んだ光がピースのカーブに反射し、壁に小さな模様を描き出した。
「うわっ…! 魔法みたいだ!」
その声に、子どもたちが集まってきた。
「ぼくもやる!」
「これはお城になるかも!」
「これ、くるくるしてる〜!」
それまで笑っていたルーカスが、ハンスの塔にそっと別のピースを足した。ぐらぐらと揺れたが、倒れなかった。
子どもたちの目が一斉に輝いた。まるで何かが始まったことを、皆が感じ取ったかのようだった。
ソフィーは自分の席に戻り、今度は横に並べて道のような形を作り始めた。
「これはね、虹のトンネルなの」
彼女はピースの隙間に指を入れ、トンネルの中に小さな木の動物を通して遊び始めた。
10個のピースで、塔ができ、橋が生まれ、迷路ができ、さらには「ドラゴンの背骨」と名付けられたうねる構造物まで登場した。
子どもたちの世界は、もう止まらなかった。
彼らは積むだけではなく、回す、並べる、傾ける、つなげる。大人が考えもしない方法でピースを操っていた。
エミリー先生が、そっとクルトに囁いた。
「クルトさん…この子たち、こんなに集中して遊ぶの、初めて見ました」
クルトは、黙ってうなずいた。胸の奥が熱くなり、言葉が出なかった。
積み木は、静かに、しかし確かに、子どもたちの想像力に火をつけたのだった。
いかがでしたか?
この章から、物語は大きく動き始めます。次は【第4章:木の声、色の誘惑】です。進
第4章:木の声、色の誘惑
試作品の反応は、想像以上だった。
あの週末以来、幼稚園では「ネフのおもちゃ」が話題となり、子どもたちは毎日、積み木の“続きを遊ぶ”のを楽しみにしていた。
園長のエミリー先生は、クルトに嬉しそうに報告してくれた。
「子どもたち、あの積み木を“ネフの魔法”って呼んでるんですよ。あれがあるだけで、遊びが変わるんです」
クルトは心の底から嬉しかった。家具で感じたことのない、静かな感動が胸を満たしていた。
そして彼は、ネフスピールの本格的な制作を決意した。
しかし、新たな課題が浮かび上がった。
「色は、どうする?」
最初に声を上げたのは、若い見習いのフランツだった。
彼は鮮やかな青や赤、黄色の塗料の缶を並べながら興奮気味に語った。
「クルトさん!やっぱりカラフルにしたほうが子どもに人気が出ますよ! 見た目で手に取る確率、絶対に上がります!」
クルトは腕を組み、黙ってピースを見つめた。
確かに、色があれば目を引くかもしれない。
売り場に並んだとき、他の玩具よりも目立つ。木の色は地味で、素通りされるかもしれない。
けれど、クルトの中で何かが引っかかっていた。
彼は静かに言った。
「でも、木そのものの美しさが消えてしまう。メープルの木目、あの温かい触感…。塗料の膜でそれを覆ってしまっていいのか?」
その言葉に、アンナがそっと割って入った。
「どちらの気持ちも分かるわ。色があれば、確かに最初の“入り口”になる。でも…子どもたちに聞いてみるのが一番じゃない?」
フランツは不満げだったが、クルトはうなずいた。
「そうしよう。子どもたちは、正直だからな」
数日後、クルトは色付きのピースと、無垢のピースを二種類準備し、再び幼稚園を訪れた。
「今日は、好きな方で遊んでみてくれ」
赤や青、黄色に塗られたピースに、子どもたちは最初、飛びついた。
「赤が一番!」「ぼくは青が好き!」と歓声が上がり、フランツは嬉しそうに笑った。
「ほら、やっぱり色付きが正解ですよ!」
しかし——30分が経過すると、様子が変わってきた。
子どもたちは色付きピースの組み合わせに飽き、だんだんと無垢のピースに手を伸ばし始めた。
「この木、あったかい匂いがする」
「なんか森みたい」
「こっちはね、自分で“虹色”を想像できるの」
ハンスはそっと、無垢のピースを頬に当てた。
「色がないから、僕の頭の中で好きな色に変えられるんだ」
2時間後。遊戯室には、無垢のピースで作られた塔と橋と物語の世界が広がっていた。
色付きピースは、片隅に静かに積まれていた。
クルトは、確信した。
「子どもたちは、木の声をちゃんと聞いている」
フランツは肩をすくめて笑った。
「やっぱり、子どもって面白いですね」
この決断が、ネフスピールの“哲学”を決定づけた。
素材そのものの美しさを信じ、子どもの感性を信じる——それが、クルトの道だった。
いかがでしたか? 次は【第5章:ネフスピールの誕生】です。
ブランド名が決まり、世に出ていく転機の章。
第5章:ネフスピールの誕生
1958年春。
工房の空気は、これまでと違っていた。まるで新しい季節が、本当に中から芽吹いたかのようだった。
クルトはついに、この積み木に名前を与える決心をした。
「ネフスピール」
“Naef(ネフ)”は自分の名。
“Spiel(シュピール)”はドイツ語で「遊び」。
2つの言葉を繋げることで、それは単なる商品名ではなく、彼自身の思想を映す旗となった。
「本物の素材を使い、子どもが自由に想像し、創造できる“遊び”を届けたい」
その理念が、たったひとつの言葉に込められていた。
制作は手探りだった。
ピースはすべて手作業。木材の選別、曲線のカット、角の面取り、仕上げの磨きまで、一つひとつ丁寧に。アンナも、フランツも、黙々と作業を続けた。
アンナは紙やすりをかけながら、ふと口にした。
「名前がつくと…不思議ね。命が宿ったような気がするわ」
クルトは微笑み、頷いた。
「そうだな。これはもう、作品じゃない。“仲間”みたいなもんだ」
完成したネフスピールは、シンプルな木箱に詰められた。
印刷や華やかなデザインはなし。ただ、木の香りと、確かな手触り。フタには「Naef Spiel」と小さく焼き印が押されていた。
最初に販売を引き受けてくれたのは、チューリッヒの小さな玩具店「キンダーヴェルト」。オーナーのリゼは、試作品を手に取った瞬間、言った。
「これは、遊びのためのおもちゃじゃないわ。遊び“そのもの”ね」
初めて店頭に並んだ日。クルトとアンナは、そっとガラス越しに様子を見守っていた。
若い母親が、小さな男の子と入ってきた。
「ねぇママ、これ、なに?」
「積み木よ。でも…形が面白いね」
少年はピースをひとつ手に取り、しばらく黙って眺めていた。そして言った。
「これで、月の基地を作るんだ!」
その言葉に、クルトは心の中で何かがはじけるのを感じた。
口コミは静かに、しかし確実に広がっていった。
「子どもがずっと集中して遊んでいる」
「触っているだけで落ち着く」
「“積む”だけじゃなく、“話す”ように遊んでいる」
そして1962年。
ネフスピールはスイス国内最大の玩具フェア「チューリッヒ・シュピールターゲ」に出展され、最優秀デザイン玩具賞を受賞した。
審査員の一人はこうコメントした。
「これは知育玩具ではなく、知“感”玩具だ。知性と感性の両方を呼び起こす、希有な存在だ」
ネフの工房には、国内外からの注文が殺到した。
一度に大量生産することはできないため、リストに沿って一つずつ、手作業で納品されていった。
フランツは驚きながら、工房のカレンダーを眺めて言った。
「来月までの注文、全部で83件…。これ、家具より売れてますよ…!」
クルトは、目を細めて答えた。
「子どもたちの声が、世界に届いたってことだな」
ある日、久しぶりにマルタが工房を訪ねてきた。
彼女は、木箱に入ったネフスピールを手に、懐かしそうに微笑んだ。
「クルト。ね、覚えてる? 私、“子どもにこそ本物を”って言ったのよ」
「忘れたことなんか、一度もありませんよ」
クルトは照れたように笑いながら、マルタの言葉を胸の奥でそっとかみしめていた。
次章は、ネフスピールが子どもの世界を飛び越え、大人たちの心も捉えていく物語です。
【第6章:静けさの中の挑戦者たち】
🧩 ちょっと小休止
ネフスピールってどんなおもちゃ?
詳しくはこちらから
(2026/02/03 01:43:34時点 楽天市場調べ-詳細)
その曲線が生み出す、想像のバランス。
一つひとつに、クルトと子どもたちの物語が詰まっています。
第6章:静けさの中の挑戦者たち
ネフスピールの人気は、子どもたちの間にとどまらなかった。
ある日、チューリッヒ市内の美術館からクルトのもとへ連絡があった。
「現代のデザイン玩具を紹介する展示を行いたい。ネフスピールをアート作品として展示したい」と。
驚きつつも、クルトは快諾した。
数週間後、白い壁に囲まれた美術館の一室に、10個のピースがシンプルに配置された。
そこを訪れたのは、芸術家、建築家、教育者、そして哲学者たち。
彼らは、一見“ただの積み木”に思えるものを前に、静かに息を呑んだ。
「なんだこれは…形が生きている」
「建築の基本が詰まっている。重心、バランス、空間の緊張と解放…」
「これは彫刻だ。しかも、手で“語る”彫刻だ」
その日以来、ネフスピールは「遊び」ではなく「構築と思考の道具」として、静かに別の層に火を灯した。
そして、その火は国境を越え、はるか遠く、日本にも届いた。
将棋の名門棋士・山中一郎九段。彼が対局前の控室で、いつも机の上に積み木を置いているという噂が将棋界に広まった。
ある雑誌のインタビューで、彼は語っていた。
「ネフスピール? ああ、これがね、頭をリセットしてくれるんですよ。無意識にバランスを取る作業が、思考のゴミを捨ててくれる。まるで盤面の“構造”と向き合ってるような感覚になるんです」
彼だけではない。数学者、脳科学者、プロのピアニスト、舞台美術家——さまざまな分野のプロフェッショナルたちが、ネフスピールを日常の中で使い始めていた。
ある数学者は、ピースの角度と曲線の交点を研究材料にし、そこから新しいアルゴリズムのヒントを得たという。
ある美術教師は「ネフスピールを使って、生徒に“描かない彫刻”を教えている」と話した。
フランツは、ある日新聞記事を読みながら呟いた。
「クルトさん…。これ、積み木っていうより、もう“道具”ですよ。子どもが遊ぶ道具で、大人が考える道具。なんかすごいことになってきてます」
クルトは笑って言った。
「それでいいんだ。“遊び”は、子どもだけのものじゃないからな」
そしてクルトは、新たな挑戦を始める。
「もっと大人も子どもも一緒に“考えて、遊ぶ”ものを作りたい」
その想いから生まれたのが、立方体の中に複数の穴と棒を通すことで、構造とリズムを学ぶ知育パズル「リグノ」。
これらもまた、ネフスピールと同じように、“シンプルだけど奥深い”道具として世界中に広まっていった。
遊びは、学びになる。
創造は、誰にでも開かれている。
ネフの哲学は、確実に人々の暮らしへ、静かに、けれど力強く根を張り始めていた。
次はいよいよ物語の締めくくり。
【終章:木の温もりは、時を超えて】
終章:木の温もりは、時を超えて
1980年代。
クルトは、ついに工房を若い職人たちに託し、第一線から静かに身を引いた。
毎朝削っていた木、数えきれないほどのスケッチ、ひとつずつ磨き上げた積み木。
すべては、彼の“遊び”の哲学と共に、今や職人たちの手によって引き継がれていた。
退いたとはいえ、クルトは決して“作ること”をやめたわけではなかった。
工房の裏にある、小さな作業室。そこにはいくつかの道具と、山積みのメモ帳、そして古びたスケッチブックがあった。
午前中は木を削り、午後は近所の子どもたちと庭で遊ぶ。
時折、積み木の新しい形を夢中で描いては、アンナに見せていた。
「あなた、本当に引退してるのかしら?」
そう笑うアンナの言葉に、彼は肩をすくめて答えた。
「創ることは、息をすることと同じなんだよ」
時は流れ、2025年。
ネフ社は今やスイスを代表する知育玩具メーカーとして、世界中に名を知られている。
ドイツ、日本、北欧、アメリカ。
ネフスピールは、どの国の家庭にも自然に溶け込む“遊びのクラシック”として根を下ろしていた。
時代は変わり、玩具の世界にもAIやスマート技術が溢れている。
けれど、木の温もりだけは、なぜか変わらず求められ続けていた。
その日、クルトの孫娘リナは、祖父の使っていた古い工房を掃除していた。
棚の奥、埃をかぶった箱の中から、1冊のスケッチブックが出てきた。
ページをめくると、見覚えのある曲線。ネフスピールの原型の図面が描かれていた。
その隣には、走り書きのような文字が残されていた。
「子どもは、遊びの中で宇宙を見つける」
リナは思わず微笑んだ。
工房の窓を開けると、外から子どもたちの笑い声が聞こえてきた。
彼らが遊んでいるのは、あの“リボンのような積み木”。
50年以上前に祖父が最初に削り出した、それとまったく同じ形だった。
リナはゆっくりとスケッチブックを閉じ、胸にそっと抱きしめた。
木の声は、まだここにある。
そして、その声に耳を澄ませる子どもたちが、今も世界のどこかで塔を積み、物語を紡いでいる。
ネフスピールは、今もスイスの工房で丁寧に作られています。
滑らかな木肌、手に吸い付くような曲線、そして無限の発想を受け止める静かな力。
(2026/02/03 01:43:34時点 楽天市場調べ-詳細)
この積み木に触れた子どもたちは、夢中で塔を積み、物語を紡ぎ、時に宇宙を探検します。
そして、大人たちもまた、その創造の熱に心を奪われていくのです。
今回の記事はここまです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
よろしければ、知育玩具に関する他の人気記事も参考に!
人気記事!
おすすめ! naef (ネフ)の定番積み木2つを紹介! 子供の 想像力を育てよう
おすすめ! naef(ネフ)の美しい積み木たち6選
おすすめ! 天才を育てる知育玩具GEOMAG(ゲオマグ)
➡️ 知育玩具の記事一覧
不要になったおもちゃを効率よく処分しよう!
 120人に独自アンケート!不要になったおもちゃの処分どうしている? -気になる他の人どうしているのか?
120人に独自アンケート!不要になったおもちゃの処分どうしている? -気になる他の人どうしているのか?
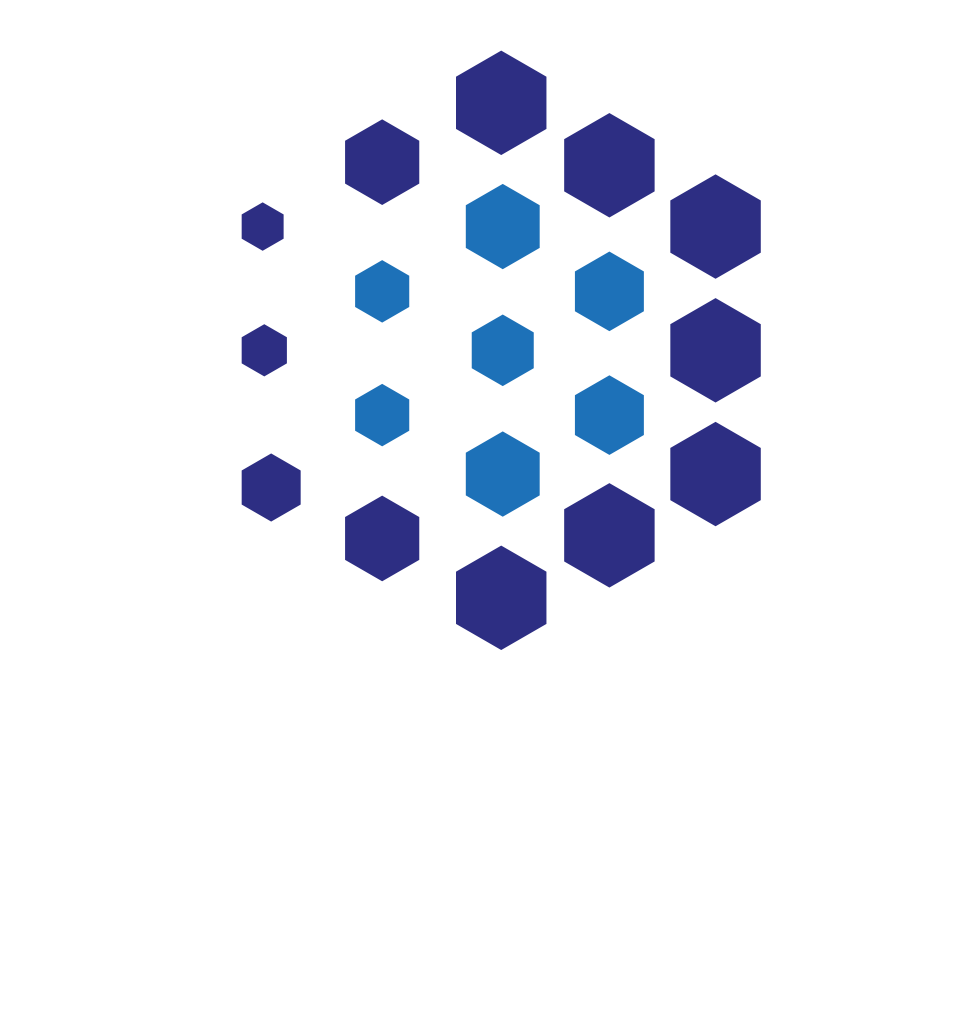 未来を担う子供をどう育てるか
未来を担う子供をどう育てるか 



